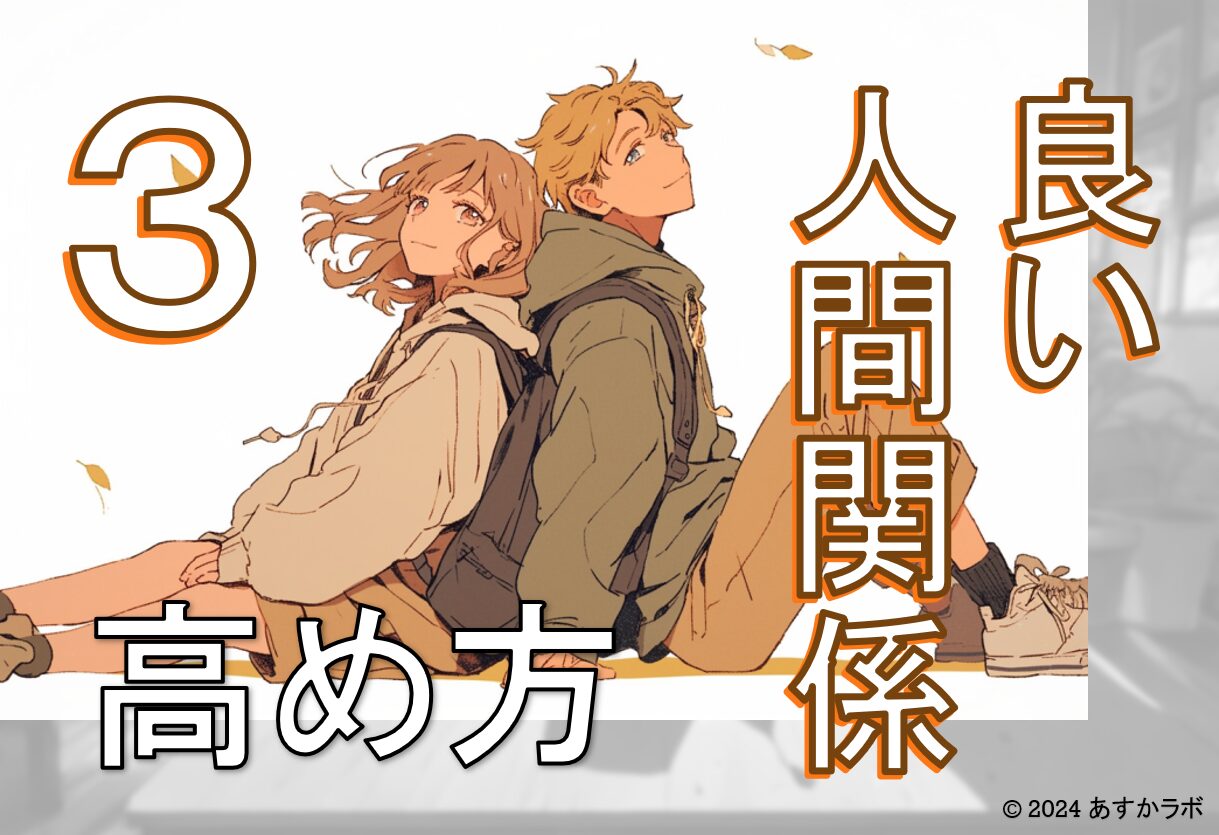個人でできるウェルビーイングを高める方法③~人間関係編~
幸せを決める6つの要素の続き(イントロ編、1ポジティブ感情編、2集中力編)です。
このシリーズでは、次の6つの要素
- 1)ポジティブな感情を高める
- 2)集中力を上げる
- 3)良い人間関係をつくる
- 4)人生の意味を見出す
- 5)達成感を高める
- 6)ネガティブな感情を減らす
という話をそれぞれの各パートで話してます。
なぜならこの6つの要素が高い人ほど、幸せな状態(ウェルビーイング)でいられるとポジティブ心理学でわかっているからです。
今回は、幸せを決める3つ目の要素「良い人間関係」について解説します。
![[図解]個人でウェルビーイングを高める方法 良い人間関係](https://askalabo.com/wp-content/uploads/2024/07/image-1100x792.png)
「良い人間関係」は、6つの要素の中で一番大事かもしれません。
というのも、ハーバード大学が約2,000人以上を対象に1938年から84年間にわたって人の一生を分析したところ、
- 幸せと相関していたのは「良い人間関係」であった
と明らかにしたからです。
つまり私たちが一番大事にすべきは、IQでもなく、お金でもない。
身近にいる人間関係を大事にすれば、幸せになれるよとハーバード大学は述べています。
以前過去記事で、年収350万の人も使い方次第で年収1億ある人より幸せになれる例を紹介しましたが、必ずしも「お金がたくさんある=幸せ」に直結しないのは面白いですよね。
実際、質の高い人間関係は
- 困ったときに周りからサポートしてもらいやすくなる
- 健康寿命が伸びる
- 80代になっても記憶力を保てる
- メンタルが安定する
などのメリットがたくさんあるとわかってます。
たしかに寿命が長い県で有名な沖縄では、みんなで助け合おうという文化(ちなみに、方言ではゆいまーるといったりします)がありますが、人間関係と寿命って密接に繋がっているのかなと思ったりします。
では、どうすれば良い人間関係はつくれるのか?
今回はウェルビーイングを上げる3つ目の要素「良い人間関係」を高める方法を3つ紹介します。
良い人間関係を高める方法

良い人間関係を高める方法は次の4つです。
【良い人間関係を高める方法】
- 1)ヘルパーズハイになる
- 2)自己開示をする
- 3)コミュ力を上げる
- 4)アダムグラントの5分ルールを使う
「ヘルパーズハイとか5分ルールとか変わった方法もあるな」と感じた方もいるかもしれないですね。
それぞれ順にみていきましょう。
良い人間関係を高める方法1)ヘルパーズハイになる

「与える人は成功する」という言葉は有名ですが、与える行為は人間関係を良くする効果もあります。
ここでいう与えるとは、
- 時間
- プレゼント
- 言葉
- 労力
- 手助け
などいろんなものを含んでます。
私たちは他人に対して何かを与える行為をすると、「ヘルパーズハイ」と呼ばれる感覚が生まれます。
この感覚を持つと、自分の不安な気持ちが減ったり、いま抱えている問題について冷静に対処できるようになります。
例えば、あなたが目の前の仕事に追われていて、とても焦っていたり不安な気持ちになっていたとします。
そのとき、あえて少しだけ誰かの仕事をサポートしてみる。
ここで「え?それだともっと忙しくならない?」と思った人もいるかもしれませんが、実は忙しい時ほど他人に親切にすると効果的です。
なぜなら脳が「自分がいま他人を助けたということは、自分には余裕があるんだ」と錯覚して、不安な気持ちが薄れて落ち着いて対応できるようになるから。
できれば、他人に親切にするなら具体的な目標があるといいですね。
- 他人に親切にする
といった抽象的なゴールよりも、
- 誰かが仕事で困っていたらサポートしよう
といった具体的なゴールを持った人のほうが幸福度は高まるとスタンフォード大学の研究でわかっているからです。(R)
自分の幸福感も上がり、助けられた相手からは感謝されて人間関係も良くなるので一石二鳥です。
自分に余裕がない時ほどヘルパーズハイは効果を発揮するので、ぜひ試してみてください。
良い人間関係を高める方法2)自己開示をする

人は自分のことをちゃんと話す相手を信頼します。
なので相手に自己開示すればするほど,自分を信頼してもらえるようになって、だんだんと人間関係が良くなっていきます。
「でも話す相手は選んだ方がいいんじゃない?」と思った方は、ナルシストやマニュピレーター(陰で攻撃する人)を避ければ大丈夫です。
見抜き方はこちらの記事でまとめてるので、必要な方は参考にしてください。
自己開示は直接会って話すだけではなく、LINEとか文面も効果があります。
自己開示と一言でいってもいくつかあるのですが、代表的なものを2つ紹介します。
1 自分の弱みを話す
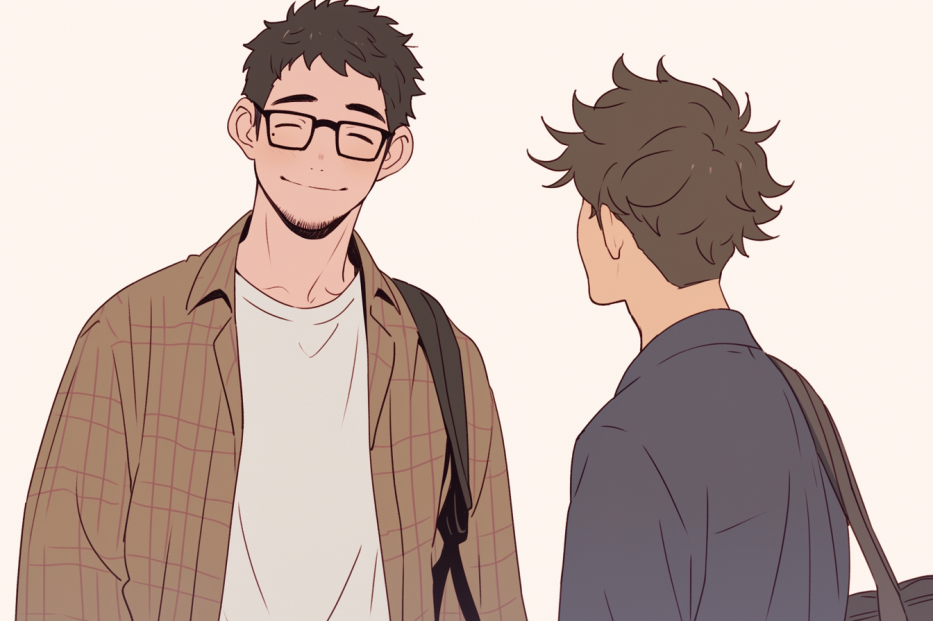
ふつうに考えて、自分の弱みを話すって自分が無能に見えるんじゃないかと心配になりますよね。
でも実は他人から見ると弱みをオープンにする人は勇気のある人に映ることがわかってます。(R)
まぁたしかに個人的な感覚としても、自分の弱みを話さない人って、自分を信用していないのかな?とか、何か隠してるのかな?って思っちゃうかなと。
- 「自分ってけっこう臆病なんだよね。だから何をやるにも優柔不断っていうか、すぐに決断できなくて」
- 「実は学生時代一度も恋人できたことないんだよね。だから恋愛に自信がないんだ」
みたいに話してくれるほうが、経験的にも当たっているように思う人は多いのではないでしょうか。
なので自分の弱みは積極的に開示したほうが、相手からは信頼してもらいやすくなります。
2 自分が改善したいことを話す

自分の弱みを見せた後にこれするとさらに信頼してもらえます。
仕事で改善したいこととか、生活習慣で改善したいことなどは深い話になりやすいので使えますね。
たとえば「自分ってけっこう口下手だから、最近思い切ってコミュニケーション講座に入って話し方の勉強してるんだよね」などと話してみる。
自分が改善したい内容を話したあと「ちなみに○○さんはどうですか?」と聞いてみる。
するとお互い深い話題を開示しあうので、親密度を高めることができます。
良い人間関係を高める方法3)コミュ力を上げる

コミュ力とは何か?それは「人としての魅力」であると明らかになってます(R)
では「人としての魅力」とは何か?
それは、大きく大別すると次の3つです。
- ①率直である
- ②感情が安定している
- ③好感度が高い
つまりコミュ力の高い人とは、素直で感情が安定していて、好感度の高い人ってことですね。
こんな人になれたらもう人間関係良くならないわけがないですよね笑
一般的には、話してて面白いとか、話がわかりやすい人がコミュ力高いと言われたりしますが、科学的にはそれよりも魅力が大事だといえます。
コミュ力を上げると、
- 苦手な人とも会話できる
- 相手に誤解なく相手に言いたいことが伝わる
- 好感度が上がってモテるようになる
といったメリットがあるので、スキルは磨いていて損はないかなと。
具体的なコミュ力のあげ方についてはコミュ力シリーズで解説してるので、詳しく知りたい方はこちらを確認してみてください。
良い人間関係を高める方法4)アダムグラントの5分ルールを使う

アダムグラントの5分ルールというのは、
- 5分以内に解決できそうなものは助けて、5分以上かかるものは助けない
といったルールをいいます。
「なんだか冷たいな」と思った方もいるかもしれませんが、実は5分という制限を設けて助けたほうが、人間関係はよくなります。
なぜなら5分という制限をつけて相手を助けるとなると、基本的に自分の得意なことでしか解決できないからです。
たとえば、上司から「この部分をパワポで作れる?」と図の作成をお願いされたとします。
これを5分ルールで当てはめてみます。
- 「5分ルール」で考える
- →図の作成が得意だから5分以内で作れる!
- →相手から感謝される
となります。
でも、パワポでの作業は苦手なのに、無理やり引き受けたらどうなるでしょうか?
- 図の作成が苦手なのに引き受ける
- →多くの時間がかかる
- →いつまでも図の作成に苦労して、どんどん自分の時間が奪われる
といった結果になってしまいます。
自分が苦手な分野なのに無理して相手をたすけると、最悪の場合「下手くそぉ!」などと怒らたりしてメンタルが傷つく。
つまり自分の苦手なことであれば相手は助けなくてもいいのです。
ほかの得意な人に任せればOKです。
5分ルールを使えば、感謝されて人間関係もよくなるのでお勧めです。
ちなみに「5分ルール」は、「アダムグラントの5分ルール」とは?自己犠牲せずに人間関係を広げる方法でも詳しく紹介してます。
もっと詳しく知りたい方は確認してください。
良い人間関係を高める方法まとめ

ウェルビーイングを高めるうえで一番大事な「良い人間関係」を高める方法まとめです。
- ハーバード大学が人の一生を追った研究によると、もっとも人の幸せと相関していたのは「良い人間関係」だと明らかになった
質の高い人間関係は
- 困ったときに周りからサポートしてもらいやすくなる
- 健康寿命が伸びる
- 80代になっても記憶力を保てる
- メンタルが安定する
などのメリットあり
【良い人間関係を高める方法】
私たちはお金をたくさんもっている人が幸せだと思いますが、実はそれ以上に人間関係が重要だったのは意外ですよね。
良い人間関係をつくれたら健康寿命も延びるのでこちらの要素も伸ばしておくと最強ですね。
自分が人生のどん底にいる時とか、仕事で行き詰っている時でも助けてもらえます。
今回紹介した人間関係を高める方法については、取り組みやすいところから実践してみてください。
次回は、幸せを決める4つ目の要素、「人生の意味を見出す」について解説します。
![[図解]個人でウェルビーイングを高める方法 人生の意味](https://askalabo.com/wp-content/uploads/2024/07/image-1-1100x798.png)
「おおーっ…なんかすごい深いテーマだなぁ…」と思った方もいるかもしれませんが、何も別に宗教的なお話をするわけではありません。
自分なりの人生の意味を見出せばOKです。
そこで次のシリーズではどうすれば人生の意味を見出せるのか?について詳しくお話できればと思います。
(次回)
(前回に戻る)
人間関係に関するよくある質問

友だちは多いほうがいいの?

人間関係は、友だちの数よりも質が大事です。
20代までは友だちの数は増やしてもいいですが、30代から質を重視するのがおススメです。(R)
【参考文献・データ等】
- ロバート・ウォールディンガー『グッド・ライフ 幸せになるのに、遅すぎることはない』
- マーティン・セリグマン『ポジティブ心理学の挑戦 “幸福”から“持続的幸福”へ』
- 鈴木裕『最強のコミュ力のつくりかた』
- アダム・グラント『GIVE & TAKE「与える人」こそ成功する時代』
- Melanie Rudd et al (2014)Getting the most out of giving: Concretely framing a prosocial goal maximizes happiness.
- Jean-Philippe Laurenceau et al(1998)Intimacy as an Interpersonal Process: the Importance of Self-Disclosure, Partner Disclosure, and Perceived Partner Responsiveness in Interpersonal Exchanges.
- Cheryl L Carmichael(2015)In Your 20s It’s Quantity, in Your 30s It’s Quality: The Prognostic Value of Social Activity Across 30 Years of Adulthood.
【記事執筆】あすか
【X(旧Twitter)】:https://twitter.com/askalabo
【note】:https://note.com/askalabo/
【Instagram】:instagram.com/aska.labo