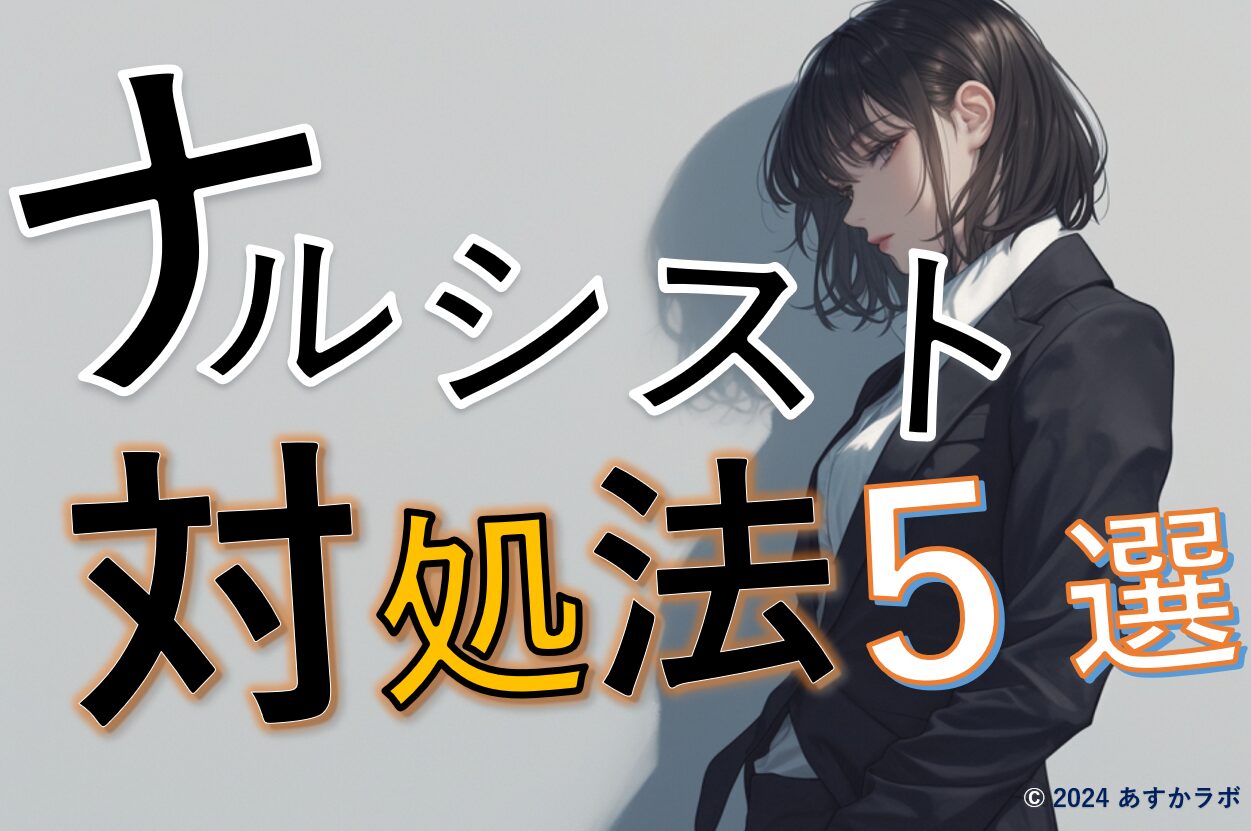ナルシストの対処法5つと特徴9つーあなたを見下す自己愛人間との接し方ー
あなたの周りには、なぜか上から目線な人っていません?
- 俺は有能だアピールする偉そうな上司
- 大企業に就職した途端、見下す同級生
- 自分のことを根掘り葉掘りきいてバカにする人
彼らのような上から目線な人は、ナルシストの可能性が大です。
ナルシストとは、
- 自己中な行動を見せたり態度をとったりする傲慢な人間
をいいます。
ナルシストの人は
- 常に自分は注目されるべき
- 特別扱いされるのが当たり前
と思っている。
だからあなたの手柄を、あたかも自分がやったかのように横取りしたりします(最低だぜ)
彼らは一見、自信たっぷりに振るまうのでカリスマ性がある人に見える。
ですが、中身がありません。
ナルシスト相手にするのってめんどうくさいですよね…。
自信がありすぎるせいで、利用されたり恨まれたりして被害に合うこともあります。
そこで今回は、明日から使える上から目線の人の5つの対処法と9つの特徴について解説します。
ナルシストの対処法については、『結局、自分のことしか考えない人たち』がオススメです。
彼らの理不尽な言動に振り回されたり、傷つけられたりしないための対策についてもっと深堀りしたい方は読んでみてください。
まずはナルシストな人の対処法5つを解説します。
ナルシストの対処法5つ

そもそも彼らナルシストへの一番根本的な対策はなんだと思いますか?
それは「相手にしない」ことです。
ですが、学校や職場が一緒とか、付き合いで話さざるを得ない場合もありますよね…。
そこで使えるのが、次の5つの対処法です。
【ナルシストな人への対処法】
- 対処法①投影の心理を知る
- 対処法②事実は伝えず持ち上げる
- 対処法③質問で投げかける
- 対処法④先にこちらから与えない
- 対処法⑤プライベートの自分は見せない
コツは、
- 真っ向から彼らとぶつからない
ということです。
スマブラでいうと、あなたはフォックスとかサムスとか遠距離タイプを選択する。
カービィやプリンみたいに近くで戦うキャラはNG ✖。
場外にぶっ飛ばされてしまいます。
なのであくまでもさりげなく、遠くから密かに対処していきます。
ナルシストの対処法①投影の心理を知る
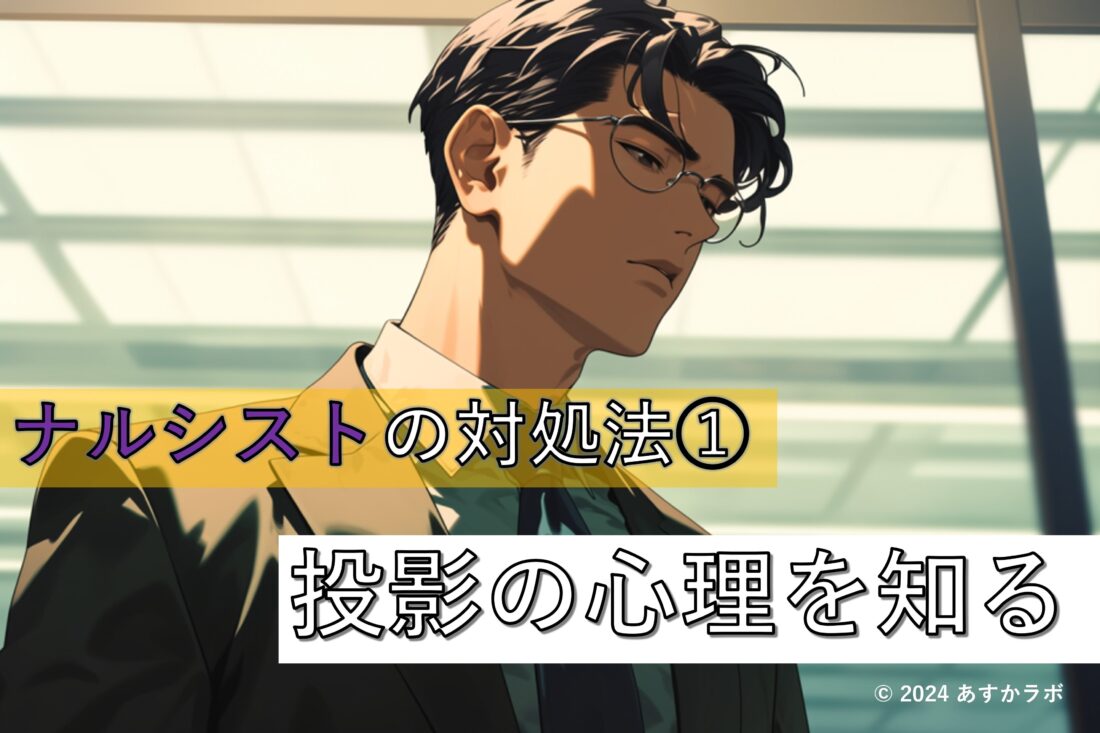
ナルシストな人への対処法1つ目は「投影の心理を知る」です。
投影とは、
- 自分の欠点や悪い面を相手がもっていると思い込もうとする
といった心理をいいます。
例えば、
- 我が強くて頑固な人が「お前我が強くて頑固だろ!」と自分のことを棚に上げて他人に指摘する
- フリフリのスカートとか年齢にそぐわない恰好をしてる人が「あの子若者ぶっちゃって」と批判する
- いつも目上の人に強く反論してる人が「そうやって上司の俺に意見いうな!」と部下に怒鳴る
まわりから見ると、「いやいやそれってあんたのことじゃん!」ってツッコミたくなる。
彼らナルシストは、自分の欠点や悪いところを認めたくない。
なので、相手にその性質をもっていると思い込ませようとします。
もし、投影の心理を知らずに彼らと接すると、
- あれ?自分ってこんな部分をもってたのかなぁ…?
と、無駄に自分を責めることになります。
でも投影の心理を知っていたら、
- 「あ、この批判って要はこの人が認めたくない部分なんだな。自分のことではないんだな」
と対処できます。
先ほどの例でいうと、
- 我が強い
- 頑固
- 若者ぶってる
- 目上の人にも強く反論する
が、実はひそかに彼らナルシストが気にしている自分の欠点(フフフ…)
なので彼らから批判されたら、その内容が自分のものか相手のものか自問する。
すると余計に自分を責めたり、イライラしたりせずに済みます。
ナルシストの対処法②事実は伝えず持ち上げる

ナルシストな人への対処法2つ目は「事実は伝えず持ち上げる」です。
相手が上司とか顧客とか立場が弱い場合に最良の対策になります。
例えば、上司がいい歳して流行りを追って若い人の曲ばかり一生懸命聴いてる。
そして
「オレは最近の流行りの曲知ってるぜ。お前ら遅れてんな。ハン笑」
って鼻で笑っている。
でもどんな曲か聞いてみると2、3年前に流行った音楽。
若い人から見ると
「流行りっていうか…逆に遅れてるよねプププッ笑」
って心の中で思う。
この時、
- 「その曲ってもう古いですよ(笑)」
と事実を伝えると、相手は俺に恥をかかせた!(笑)ってなんや!と感じて恨まれる。
だから持ち上げます。
- 「え?めっちゃ今時ですね!私もその曲(懐かしすぎて笑)知りませんでした!今度教えてくださいよ!」
とリアクションする。
学生時代運動部だった人は、体育会系のノリでできるかもしれません。
でももしあなたが称賛するのが苦手なタイプだったら?
その場合は、傾聴しているフリも効果的です。
興味をもっているかのように
「ほぉ~ん」
とウンウンうなずいたり、相手の言葉を
「サイキンノ キョクヲ シッテイルノデスネ!」
と、Shiriみたいに繰り返す。
すると相手は大喜びするので、あとで恨まれて攻撃される危険性もなくなります。
リアクションが苦手な人もできる対処法ですね。
ナルシストの対処法③質問で投げかける

ナルシストな人への対処法3つ目は「質問でなげかける」です。
恥の感情を強く持つ彼らは、直してほしいところを直接伝えるとどうなるか?
「自分は攻撃された!」と感じて反発します。
ですが、質問で投げかけると攻撃されたと感じません。
なぜなら自分で考えた、自分の内面から湧き上がってきた感情は否定できないからです。
だから断定してアドバイスせずに、
- 「こうしたらもっとあなたに注目するんじゃない?」
- 「もしこのまま何もせずに評判が落ちたらどう思う?」
- 「こうすればあなたに憧れる人が増えるんじゃない?」
と質問して対処する。
すると、
「早く動かなきゃ!」「やばばばばば!」
となって、これまで奈良の大仏みたいに動かなかった人が光の速さで動く。
逆に、ナルシストに指摘するのは禁句。
何故かというと、あとで必ずやり返しにくるから。
だから
「まわりはどう感じると思う?」
「こうすればもっと君の良さに気づくんじゃない?」
と質問します。すると動いてくれます。
ナルシストの対処法④先にこちらから与えない
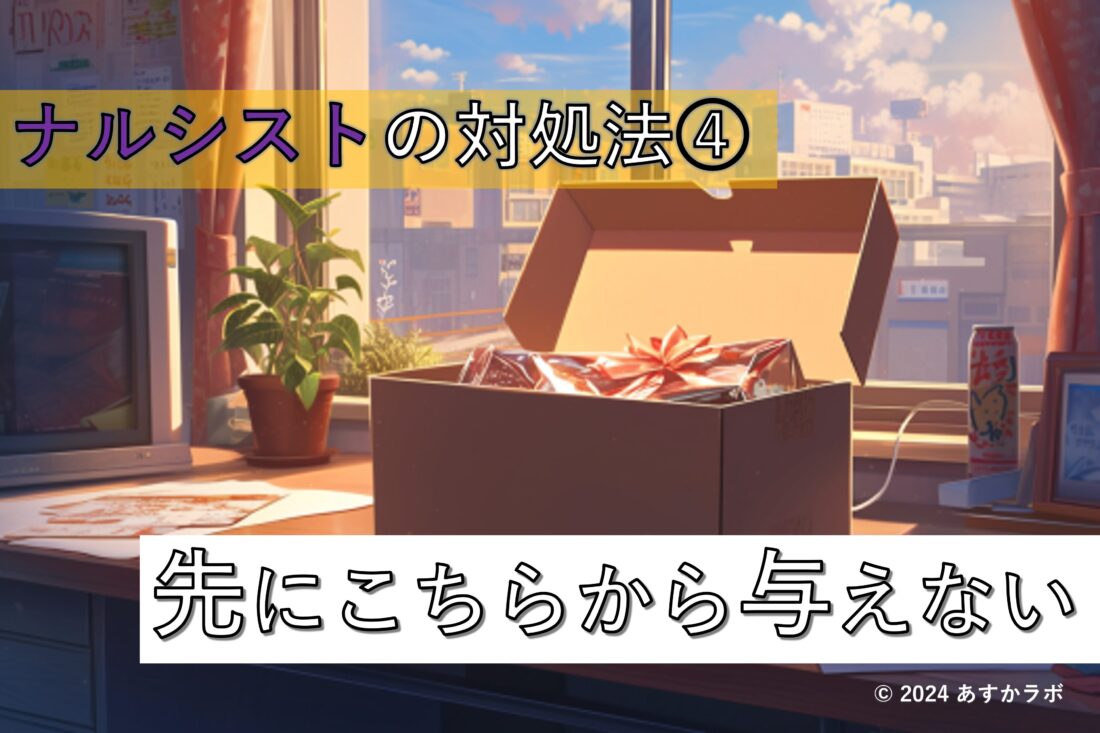
ナルシストな人への対処法4つ目は「先にこちらから与えない」です。
彼らナルシストとは、ギブ&テイクの関係が作れません。
- 「自分は与えられて当然。尽くしてもらって当然。なぜなら自分は、特別で、素晴らしい存在だから」
と考えます。
与えるよりも多くを奪おうとするテイカーのような考え方をします。
つまり先に与えてしまうと、そのままあなたの労力がごっそり持っていかれてしまいます。
彼らは口がうまいので
「あなたの力が必要だ」
とか言っていつの間にか自分が先に提供している場合もあります。
だから相手がナルシストの場合は、
- 確実に手に入れたと判断したうえで自分が返す
- 絶対に先に与えない
を徹底します。
彼らに流されないコツは、「行動」で見ることです。
相手がなにかを自分に差し出した、物を提供したと行動で確認できたら自分もお返しします。
こういうと
「私のこと信用してないんだ!ひどいね!」
と思われるんじゃないかと心配した方もいるかもしれません。
ですが面白いことに、先に与えなくても彼らから恨まれることはありません。
理由は、
- 「自分が何か提供すれば、確実にもってきてくれるわ簡単笑」
と思われてむしろ印象が良くなるからです。

なんかナルシストの人って、不思議で面白いよねー。
一周回って好きになっちゃうぜ笑
ナルシストの対処法⑤プライベートの自分は見せない

最後、ナルシストな人への対処法5つ目は「プライベートの自分は見せない」です。
自分と他人の境界線が皆無な彼らは、あなたのプライベートの情報も当たり前のようにききまくります。
ナルシストの人は常に自分が優位であることを認識していたい。
なので、なにか弱点をみつけて優越感に浸ろうとします。
逆に、
- 旅行に行った
- 彼氏とデートした
- サークルでバーベキューした
とか充実した休日を想像させるような内容を話すと妬まれるのでやっかいです。
相手に劣等感をかんじさせず、かつ自分のメンタルを守るためには、
- 家でゆっくり過ごした
- 映画を観た
とか無難な話をして、プライベートな自己を見せないよう徹底します。
つまり、
- ナルシスト相手には気づかれないように仕事と私生活の境界線を守る
すると嫌な気分や落ち込んだ気持ちを引きずらなくて済みます。
ナルシストの特徴9つ

あなたの周りにいる人が、どんなタイプだったらナルシストなのか?
彼らの特徴についても紹介します。
自己愛の強いナルシストな人の特徴は次の9つです。
【ナルシストの特徴】
- 特徴①責任転嫁する
- 特徴②傲慢な態度で見下す
- 特徴③特別扱いと称賛を求める
- 特徴④プライベートな情報を知りたがる
- 特徴⑤壮大なビジョンを語る
- 特徴⑥えこひいきする
- 特徴⑦徹底的に他人を利用する
- 特徴⑧感情のアップダウンが激しい
- 特徴⑨嫉妬心が強い
もうこの特徴を見るだけでもヤバさが伝わりますね…。
早速ナルシストの特徴について見ていきましょう。
ナルシストの特徴①責任転嫁する

ナルシストの特徴1つ目は「責任転嫁する」です。
恐ろしいことにナルシストの人は罪悪感を感じません。
なぜなら「自分は何も悪くない」と考えるからです。
でも「恥の感情」は強く感じます。
彼らは恥の感情を受け入れたくないので、
「これは私の責任じゃない!」
といって他人に責任を押し付けたりします。
例えば、部下が作った資料の中身を確認せず上司がそのままハンコを押して決裁したとします。
それであとで部下が作った資料に重大なミスがあったことに気づいたら、
「お前を信じて決裁したのに、なんでちゃんと確認しなかったんだ!」
と責任転嫁する。
「確認しなかったのはあなたやん」
って周りは思う。
けど、彼らは自分の恥の意識を受け入れられないので、激しい怒りを爆発させて相手を非難したりします。
ナルシストの特徴②傲慢な態度で見下す
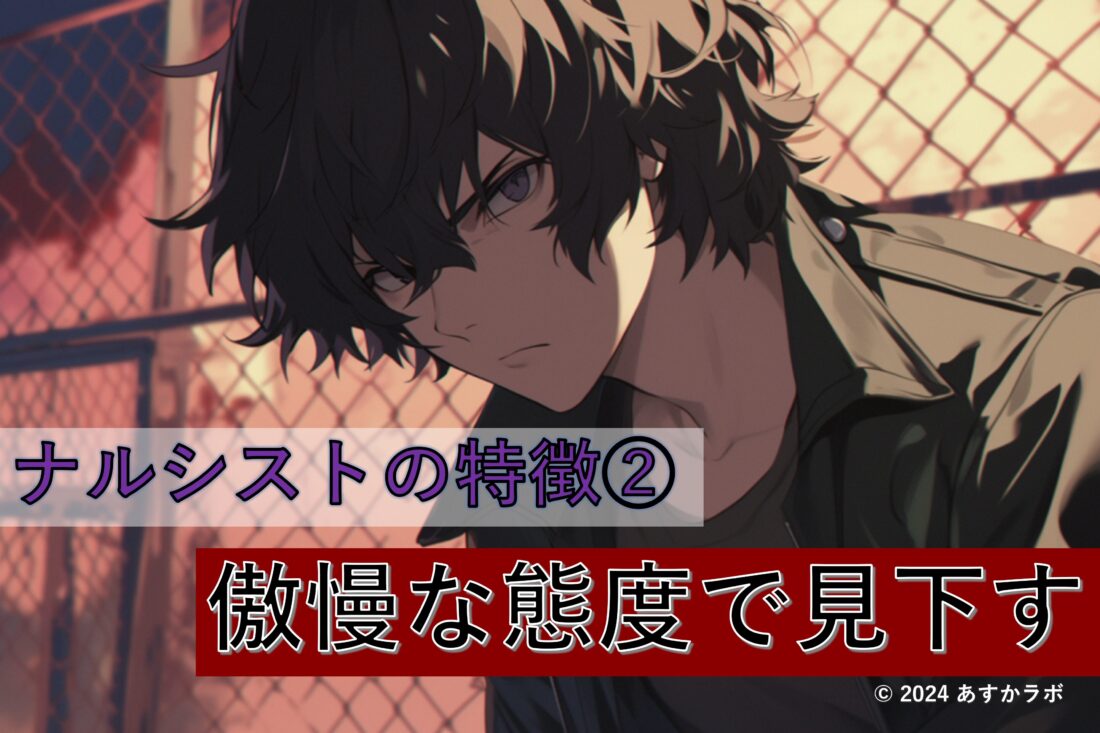
ナルシストの特徴2つ目は「傲慢な態度で見下す」です。
立場や社会的地位も同じなのに、ナルシストの人って上から目線で見下した言い方をします。
例えば、
- 「なんでこんなクソみたいなレベルの大学に俺がいるんだよ」
- 「もし俺が起業したらお前採用するわ」
- 「年収300万とか。フン笑 負け組じゃん」
などと言ったりします。
もう形状記憶されたかのように常に口角が上がってほくそ笑んでる。
不思議なことに、その人よりも高い成果や社会的地位をもってても、
「お前にしてはよう頑張ったほうじゃね?」
などと謎の自信で上から見たりします。

ナルシストな人って人を見下して「自分は有能なんだ」と思い込もうとしてるんだろうね。
ナルシストの特徴③特別扱いと称賛を求める
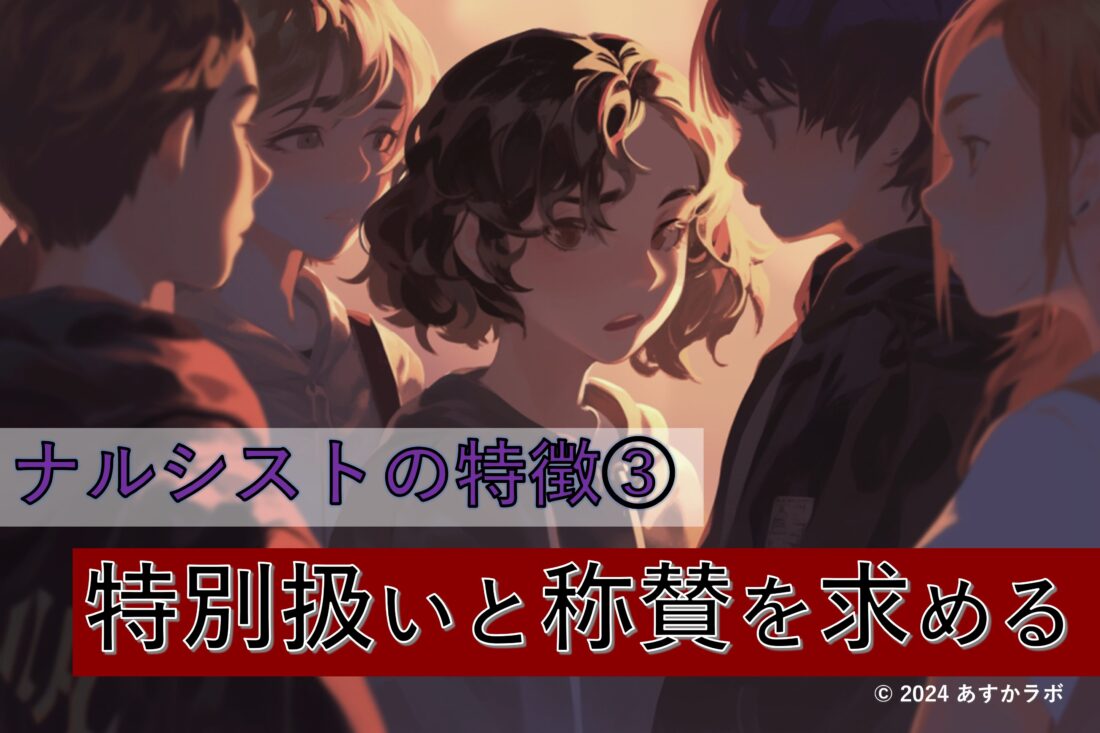
ナルシストの特徴3つ目は「特別扱いと称賛を求める」です。
自己愛の強い彼らは、常に自分にスポットライトが浴びていないと不機嫌になります。
誰かとグループで話していて、さっきまで自分の話にみんなが注目してた。
だけど話題が変わって別の人が中心になって話してたら嫌そうな顔をする。
「この私を差し置いて、あいつの話を優先させるなんて何様なんだ!」と思う。
また、彼らは特別扱い以外にも常に称賛を求めます。
- 自分はいつも周りから褒められるのが当たり前
と思っていて、大げさに褒めるとわかりやすく喜んだりします。
グループで話しているときも自分の話ばかりしかしないとか、別の人が話をしていると不機嫌になったら、ナルシストの可能性大です。
ナルシストの特徴④プライベートな情報を知りたがる

ナルシストの特徴4つ目は「プライベートな情報を知りたがる」です。
自己愛の強い彼らは、自分と他人の境界線がほぼありません。
ノックしないで普通にドアとか開けたりする。
また、相手は自分の思い通りに動くための身体の一部と考えています。
そのため、たとえ仕事同士の関係であっても、必要以上にあなたのプライベートや交友関係を細かくチェックしようとします。
束縛気質やストーカー的な要素をもっているのも、ナルシストの人の特徴だといえますね。
実際、
- 休日はどう過ごすのか
- パートナーはいるのかどうか
- 好みのタイプは何か
- どんなジャンルの映画が好きか
など事細かにあなたの情報を把握しようとします。
そして相手の弱みを見つけたら、上から目線で辱めたりします。
「こいつ彼女いないから休みもぼっちかよ。寂しいなおい笑」
といって、事あるごとに蒸し返してネチネチいじって見下してきます。
そして優越感にひたって、
- やっぱり俺って周りと比べて価値のある人間だぜ
と確認しようとします。
ナルシストの特徴⑤壮大なビジョンを語る

ナルシストの特徴5つ目は「壮大なビジョンを語る」です。
ここでいう壮大なビジョンとは、社会的意義とか世の中のためになるような夢ではありません。
彼らの個人的な野望から生まれるものです。
例えば、
- 何十億、何千億と稼いで一夫多妻みたいな生活を送りたい
- 俺の力で世の中を思い通りに動かしたい
- お金で人間をコントロールしたい
などです。
経営者の場合、その個人的な野望を達成するために従業員を働かせたりします。
また、ナルシストは口がうまい人が多いので、従業員に夢を見させることもできます。
でも、実際には自分の野望を叶えるための道具としか思ってません。恐ろしいですね。
ナルシストの特徴⑥えこひいきする

ナルシストの特徴6つ目は「えこひいきする」です。
認められたい願望が強いナルシストは、自分のことを立ててくれる人に対してえこひいきします。
上司の場合、それがたとえ会社にまったく貢献しない無能な社員であっても、自分が特別な存在だと思わせてくれる人を昇格させたりします。
「さすがですね!」
「やっぱ○○さんは凄いですね!」
と褒めるだけの人を隣に置く。
自分の承認欲求を満たしてくれる人を近くに置く。
ほかに会社にめちゃくちゃ貢献してる優秀な社員がいるのに、その人たちは評価しない。
それどころか、自分の立場を脅かす存在として逆に怒鳴り散らしたり、文句をいったりして理不尽な扱いをしたりします。

自分のプライドを守るために有能な人を排除するのかぁ…。
社会の悪や。
ナルシストの特徴⑦徹底的に他人を利用する
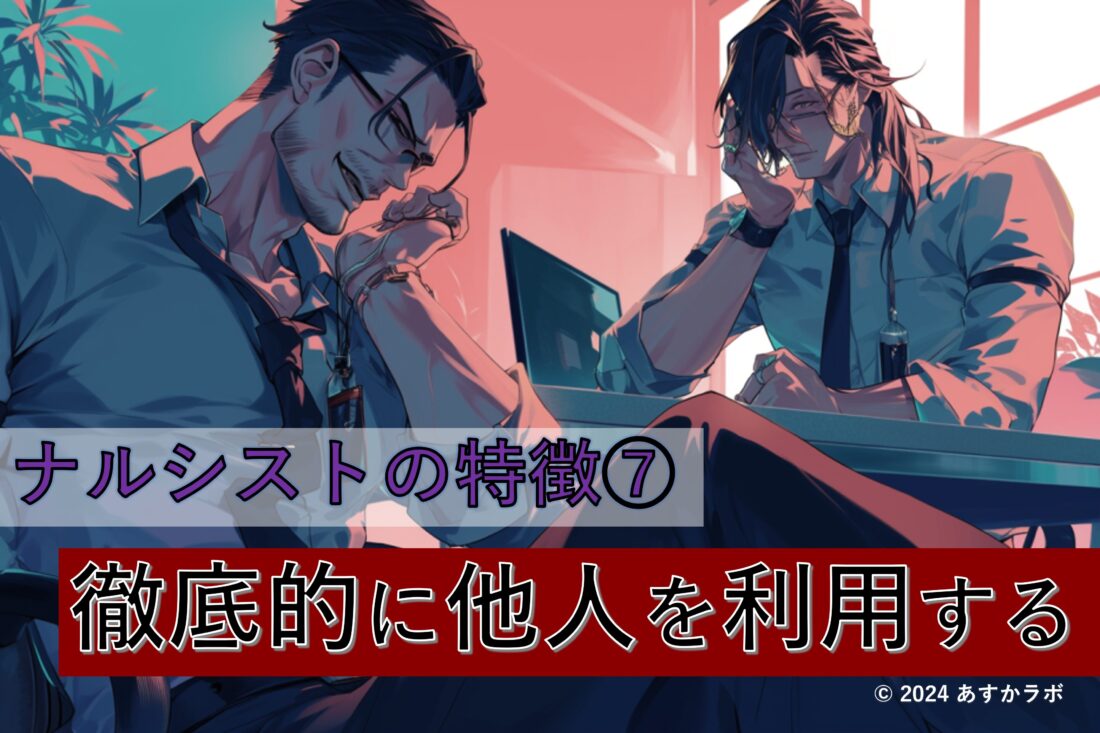
ナルシストの特徴7つ目は「徹底的に他人を利用する」です。
自己愛の強い彼らは、共感力が全くありません。
そのため平気で他人を利用します。
たとえば、従業員を朝から深夜まで働かせたりします。
週末や休暇もなく、病気でも休めない。
長時間労働も当たり前で、もうブラック企業みたいになる。
でも彼らナルシストにとっては自分のために働いてもらうのは当たり前なので、罪悪感なんて1ミリもない。
利用価値があるかないかでしか従業員をみていない。
もしあなたの会社の社長がほぼ実現不可能な夢を語りだしたら、その人は自己愛の強いナルシストな可能性があります。
ナルシストの特徴⑧感情のアップダウンが激しい

ナルシストの特徴8つ目は「感情のアップダウンが激しい」です。
日によって機嫌が異なるので、周りの人は常に顔色をうかがいます。
彼らは感情が抑えられなくなると、
- 大声を張り上げる
- 不機嫌になる
- 八つ当たりする
など、まるで子供のような態度をとります。
意外にもこれらの特徴は若い人ではなく、40代とか50代とか年齢を重ねるほど顕著にみられます。
ナルシストの特徴⑨嫉妬心が強い

最後、ナルシストの特徴9つ目は「嫉妬心が強い」です。
たとえば自分の友達が結婚して、
「結婚したの?おめでとう~!!」っていう。
でも目が笑っていない。言ってることと表情が一致していない。
心の中では
「「な、なんであんたが結婚できて、私は結婚できないのよぉー!ムキー!」」
と嫉妬心でメラメラ燃えている。
酷い人になると、友達の結婚相手の旦那さんを誘惑して関係を壊そうとする。
でも奪うことに成功したらポイって捨てる。(最低だぜ)
友達の幸せを素直に喜ばず嫉妬するような人は、実はナルシストなのかもしれません。
だからもうその人とは友達やめたほうがいい。
ナルシストの対処法と特徴まとめ

上から目線であなたを見下すナルシストの特徴と対処法のまとめです。
- ナルシストとは、自己中な行動を見せたり態度をとったりする傲慢な人間をいう。
【ナルシストな人への対処法】
- ナルシストの対処法①投影の心理を知る
- ナルシストの対処法②事実は伝えず持ち上げる
- ナルシストの対処法③質問で投げかける
- ナルシストの対処法④先にこちらから与えない
- ナルシストの対処法⑤プライベートの自分は見せない
【ナルシストの特徴】
- 特徴①責任転嫁する
- 特徴②傲慢な態度で見下す
- 特徴③特別扱いと称賛を求める
- 特徴④プライベートな情報を知りたがる
- 特徴⑤壮大なビジョンを語る
- 特徴⑥えこひいきする
- 特徴⑦徹底的に他人を利用する
- 特徴⑧感情のアップダウンが激しい
- 特徴⑨嫉妬心が強い
・常に自分の方が上だと見せつけようとする
・自分の優位性を示そうする
などをされたら、その人はナルシストの可能性があります。
彼らは直接指摘すると反感を買われて恨まれます。
なので、今回紹介した5つの方法を使って対処すると上手く対応できます。
表面的には相手が自分を思い通りに動かしているように思わせて、実は自分がコントロールしている状態にもっていくのが彼らとの賢い付き合い方です。
「この人ナルシストかな?」と思ったら、先ほどのテクニックを使ってみてください。
ナルシストの対策については『結局、自分のことしか考えない人たち』がお勧めです。
ナルシストな人への対処法として多くの人に読まれている本です。
ナルシストなあいつを思い通りにコントロールしたい!上手く立ち回りたい!と思う方は必ず参考になるので読んでみてください。
☆★☆★☆★☆
最後まで読んで頂きありがとうございました。本や論文の知識に関する情報はX(旧Twitter)やnoteでも発信してます。よかったらフォローして読んで頂けると嬉しいです↓
【X(旧Twitter)】:https://twitter.com/askalabo
【note】:https://note.com/askalabo/
関連記事:こちらも学んでおくと、上から目線の上司からナメられなくなります。「あ、こいつヤバい」と思わせることができる対処法を知りたい方はこちら↓
ナルシストに関するよくある質問

逆にナルシストのメリットってあるの?

他人から認められたい欲求や理想の自分でいたいと思っているので、努力するところは美点ですよね。
ものごとに積極的に取り組んだり、つねに確信をもって行動できます。
ただ、これがヤバい方向に動くと、偉そうな態度になって嫌われたり、他人を見くびった態度をとったりするので問題です…。
だから彼らと接するときって対策が必要なんです。
【参考文献・データ等】
- サンディ・ホチキス『結局、自分のことしか考えない人たち:自己愛人間への対応術』
- Sam Poole(2018)“Insight Hogan Development Survey (HDS)”
【記事執筆】あすか
【X(旧Twitter)】:https://twitter.com/askalabo
【note】:https://note.com/askalabo/
【Instagram】:instagram.com/aska.labo